こんにちは。
日本アドラー心理学振興会代表の田山です。
いつもブログを読んでくださりありがとうございます。
私も現在、子育て中ということもあるのか、子育てに関するご相談もよくいただきます。
とくにまだ小さいお子さん(0~3、4歳くらい)のお子さんとどう関わるかについてはよくご相談を受けるんですね。
もちろん私も日々試行錯誤なもんで、えらそうなことは何も言える立場ではないのですが、いちおう我が家はアドラー育児を実践しているし、ゼロ点ではないと思う…と自分を勇気づけながら少しでも役に立ちそうなことが在庫であればお伝えしております。
子どもの相談でよくあるのはやはり「イヤイヤ期」について。
ヤダヤダと子供に抵抗されて親が困るパターンですね。
今日は実際田山家出会ったケースを例に、イヤがる子どもとどう関わるかについてお話しようと思います。
先日ね、私の実家である仙台にしばらく帰省をしておりました。
家族団らん、私も妻の有沙さんも2歳の娘も、私の父と母もいる中、そろそろおむつを替える頃かなと確かめると、(あら、これは大かな)となったわけです。
私「おむつ替えようか」
娘「イヤ、イヤなのぉ」
娘はそう言って暗い台所に逃げ込んでいったんですね。
最近そういえば誰がやってもおむつ替えをどうも嫌がるなぁと思いつつ、いつもなら「ほら、替えるよ!」と何度も言って、それでも「イヤ!」となって、おむつを替える替えないの戦いをよく起こしていたところ、ちょっと立ち止まって考えました。
考えた末、私は暗やみにたたずむ娘にこっそりと話しかけました。
私「もしかして、みんなの前でおむつ替えたくないのかな?あっちのお部屋でおむつ替える?」
娘「…うん!」
なんと快くおむつを替えるとお返事をしてくれたんですね。
私は思いました。ああ、恥ずかしかったんだな、そりゃそうだよね。みんなの前で自分がパンツ降ろされたらそりゃはずかしいよな。それは娘もきっと同じなんだろうな、と考えたわけです。
恥ずかしながら、アドラーの言うところの「相手の目で見て、相手の耳で聞いて、相手の心で感じる」ということができてなかった。そして娘がそのことを改めて教えてくれたような感じがしました。
私「じゃあお部屋行こうか」
娘「うん!(小走りで行く)」
別室では娘もとても協力的におむつ替えに協力してくれました。
そのことをその後に妻の有沙さんに言ったんです。
有沙「ああ、確かに保育園でも隅で隠れておむつ替えするもんね。そういうことだったんだ」
そう話していました。
私たち大人は子どもがイヤがるとすぐ「イヤイヤ期だ」と片づけてしまいがちだと思うんです。
でもそれは大人側の感覚だけで、「子どもはいうこと聞くべき」とか「子どもはまだものごとをよく理解していない」とか「大人のような感情の感じ方はまだしない」など、大人の都合だけで子どもを「扱おう」としているのかもしれません。
子どもの立場で考えれば、「イヤイヤ」の背後にはそれなりの理由があって、その中にはもちろん自己中心的で、社会のルールの中では許容しがたいたくさんこともあるかもしれないけど、全部がそうではない。
中にはちゃんと理由を聞いてみると、大人も納得できる理由があったり、大人も子どもも協力できる部分がたくさんあるんです。
その「お互い協力できるところ」を子どもであろうが言葉にして話し合っていく、「扱う」のではなく「関わっていく」ということを忘れたくないなと思います。
あなたはどうですか?子どものイヤイヤを「イヤイヤ期」と片づけていませんか?
一歩立ち止まって、子どもに理由を聞いてみるとか、「もしかして〇〇かな?」と話しかけてみてください。
どっちが上下ではなく、平等な横の関係で協力をしていきたいですね。
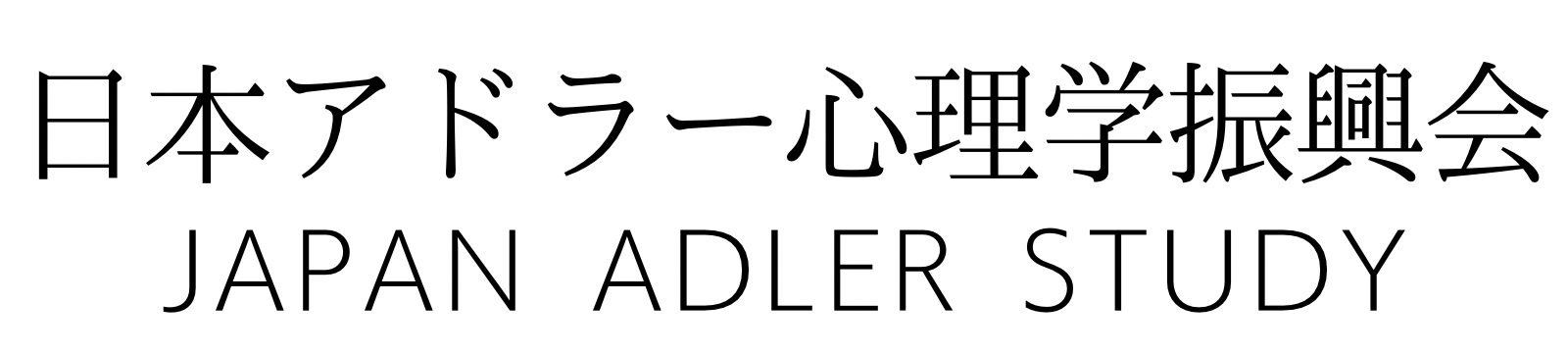

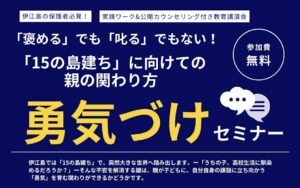



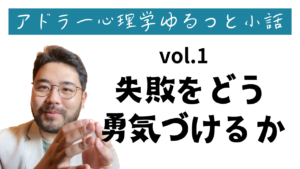


コメント