こんにちは。
日本アドラー心理学振興会代表の田山夢人です。
いつもブログを読んでくださりありがとうございます。
よくカウンセリングで、こんなことを聞きます。
「夫(妻)の浮気のせいで信じたいけど信じられない」
「子どもが嘘ばかりつくから信じたいけど信じられない」
この「信じたいけど信じられない」のパターンが出るたびに、私は思うことがあります。
「心で信じようとするのではなく、行動で信じようとする」
そう考えてほしいなと思うんです。
今日、2歳になった娘とこんなことがありました。
娘は体調不良気味でしばらくお昼寝をしていて、私と妻はリビング過ごしていました。
しばらくすると私の背後の方からドタドタドタと足音が聞こえてきたんです。
(お、娘が起きたかな?)
寝起きで髪の毛がぼさぼさの娘が急いだ様子で登場しました。
いつも昼寝から起きるときは、何やら急いでこちらに来るんです。なんともハートフルですね。
娘は私のところにきていいました。
娘「ピンポン、きたよ」
私「ん?ピンポン?きたの?」
私たちは起きていましたが、ピンポンは鳴っていません。おそらく夢で見たのかなと、その時の私は思っていました。しかし娘の行動は止まりません。
私「はーい、いきましゅ。ピンポンね」
玄関の方を指さし、私の手を引っ張りながらグングンと向かいます。
私「ピンポンか。はいはい、行きましょう」
私もついていくことにしました。
玄関につきまして、私は玄関のカギをあけてドアを開けることにしました。
私「ドア開けようね。(ガチャ)あれ、誰もいないな」
娘「いないなぁ」
私「もういっちゃったのかな」
娘「かなぁ」
ピンポンは来ていないので誰もいるはずもないのですが、ひとまず娘も納得したのかどうなのか、「戻ろう」となってリビングに一緒に戻りました。
…とまあ、なんてことのないエピソードなんですが、これがもしアドラー心理学を学ぶ前の私だったら、娘が「ピンポンきた」と言った時点で、「来てない来てない。気のせいだよ、何言ってんの」と発言をすぐに否定していたと思います。
娘が思ったことよりも、私の方が事実を知っている、私の方が正しいと思い、自分の意見を通そうとしたと思います。
でもアドラー心理学を学んで、まず「真実かどうかはどうでもいい」「正しい間違っているで判断しない」ということを学び、同時に「相手を信頼し、協力する」という「横の関係」を学びました。
ピンポンが鳴ったという娘を、私はどう信じ、どう協力ができるだろう、そう考えることができるようになったんですね。
もちろん、このとき私の心の中では「ピンポンは鳴っていない」と思っていました。でもそれは娘との「よい人間関係」を考える上で、あまり重要なことじゃないと思うんですね。
じゃあ、行動で娘を信じるとしたらどんな行動になるのか。
色んな選択肢があると思いますが、この時の私は「一緒に玄関に行き、ドアをあける」という選択をしました。私なりの「行動で信じる」ということですね。
以前、私の尊敬するアドラー心理学の先生がおっしゃるお話で、統合失調症患者さんの診察のお話がありました。
患者さんは診察室に入るや否や、「天井裏からスパイが私を狙っている」といったそうです。
普通なら「そんなわけありませんよ。さあ、気にせず診察しましょう」となると思うんです。
でも、先生はそれでは治療は進まないとおっしゃっていました。先生は実際どうされたかというと、
先生「それは大変ですね。隠れてください」
そういってハシゴを持ってきて、実際に天井裏を確認しようとしたのです。すると患者さんが言いました。
患者「ハハハ!先生やめてよ、冗談ですよ」
そう答え、その後の患者さんとの関係はかなり打ち解けて、治療がとてもスムーズに進んだそうです。
ラポールですね。信頼関係。
もし嘘をつくような相手と、今後「よい人間関係」を築いていこうと思うのなら、まず信じないといけません。
「疑う」という行為の先に、「よい人間関係」はありません。
心で信じられなくてOKです。まずは行動として信じればOK。
先生もまさか天井裏にスパイがいるとは思っていなかったと思います。でも、「信じた行動」を取ったのです。
「信じる」ということを実践するとき、私たちに必要なのは「信じた行動を取る決心」なのかもしれません。
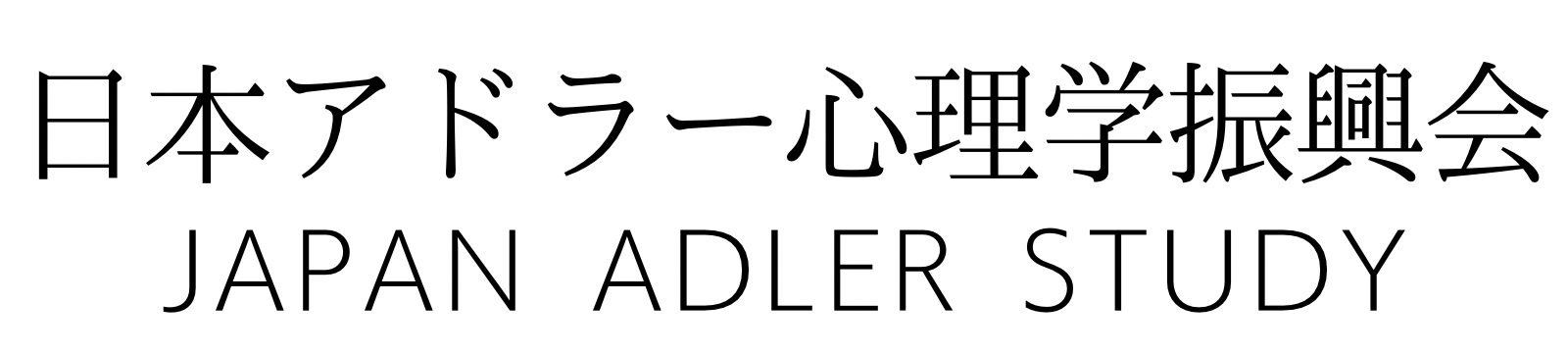

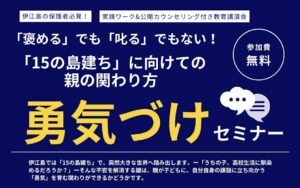
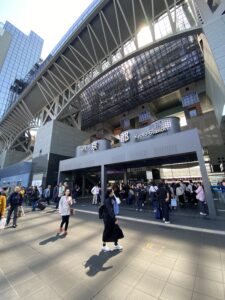


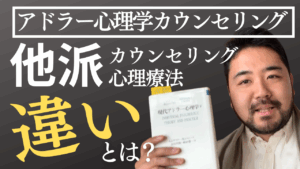



コメント