こんにちは。
日本アドラー心理学振興会代表の田山夢人です。
いつもブログを見てくださりありがとうございます。
今日は「モラハラ」について。
モラハラとは「倫理や道徳に反した嫌がらせ」という意味で、一般には「見えない暴力」といわれることもあります。言葉や態度などによって、相手を精神的に攻撃して傷つける行為ですね。でもモラハラをしている側というのは、あまり自覚がないということも多々あります。
日々、夫婦カウンセリングを多くしていますと、この「モラハラ」という言葉はよくご相談内容で出てきます。
モラハラというと、「モラハラ夫」という言葉がすぐ浮かぶ方も多いと思うし、主には男性側が女性側にする行為として世間では認知されているようにも感じます。
でも実は同じくらい「モラハラ妻」もいるんですよ。
実際に相談を受けていて、「モラハラ夫」と「モラハラ妻」の割合は半々くらいです。(黒川カウンセリングオフィス調べ)現代、この「モラハラ」に性別は関係なくなっなってきたのかもしれません。
しかし、私はみなさんにひとつ提案をしたいんです。
「モラハラ」という言葉を一旦横に置き、「自責思考・他責思考」という考えを取り入れてみませんか?
カウンセリングをして、夫婦関係を改善という目標に進めていく上で、この「モラハラ」という言葉は非常に進みを悪くしてしまう実感があります。なぜなら、「悪いあの人、かわいそうな私」という構図ができあがってしまうから。
アドラー心理学で言うところの「縦の関係」になってしまい、関係性が「協力」ではなく「争い」になってしまうんですね。
どちらが正しいか、どちらが間違っているかの「争い」のスタンスでは、何をどうしても関係は改善していきません。このスタンスの限り、相手の中に問題を見出そうとする態度が続くことになり、より関係が悪化していきやすいです。
しかし、「自責思考・他責思考」という考え方を取り入れると、わりと自分の問題にフォーカスできるようになります。つまり、「自分のあり方」にも注目して、自分の過ごし方を工夫していくことができるようになるからです。
モラハラが絡む夫婦カウンセリングをしていますと、実に多くのご夫婦が「他責思考・自責思考」の組み合わせのことが多いです。黒川カウンセリングオフィスの割合としてモラハラに関するご相談の9割はこの組み合わせです。
モラハラする側は他責思考傾向が強く、そしてモラハラで苦しむ側は自責思考傾向が強い。もちろん当てはまらない方もいるかもしれませんが、そういう方はひとつの捉え方として参考にしていただければと思います。
つまりどういうことかというと、アドラー心理学の基本的な考え方として「他人と過去は変えられない。変えられるのは自分だけ」、これは今や心理学全般にもいえることですが、その前提を踏まえると、モラハラをしてくる相手側の問題は、究極的には相手の問題です。自分が変えられるものではありません。自分が変えられることは、自分の考え方や行動ということになります。
モラハラで苦しむ側は自責思考的な傾向が強いということですから、苦しむ側の自分自身の問題としては、「相手からの責めをしっかりと受け止めて、それらを使って、さらに自分で自分を責めていく」という問題があると考えることもできます。(私はもろに自責思考で、その傾向も強かったです笑)
10人中10人が当てはまるわけではありませんが、相手の態度や言動に対して、マイナスな感情や思考を上乗せして受け取る努力をしているんですね。
カウンセリングをしていての肌感覚としては7割の方は、自分を責めることで、受けて落ち込んだり傷つくところを見せることで、相手の行為を止めようとしたり、自分を守ろうとしたり、ときにその姿を復習的に見せつけようとしたりする目的があって、その手段として「自責思考を使っている」というケースが多いです。
クライエントさんたちも「あ、確かに言われてみるとそうですね」と笑いながらお話しくださることも多いです。
だから、もしパートナーがモラハラ気質で、自分がしんどくつらくなるのであれば、「相手は他責思考的なコミュニケーションなんだな」「私は必要以上に自分でも自分を責めているんだな」「私は受け取らなくていいんだな」「相手の評価で自分の価値を決めない」と、そう思うだけでも、30~40%、場合によっては50%はしんどさや辛さは減っていくこともあります。
私がある方から言われて印象的に残っている言葉で、「傷つくかどうかも、自分で決めることができる」という言葉がありました。
相手は確かにモラハラ的な態度や言葉を投げてくるかもしれない。でもそれを受け取るかどうかは、あなたが決められると、私は信じています。
自分のあり方、もう一度考え直してみませんか?
この先もそのお相手と過ごそうと決心しているのなら。
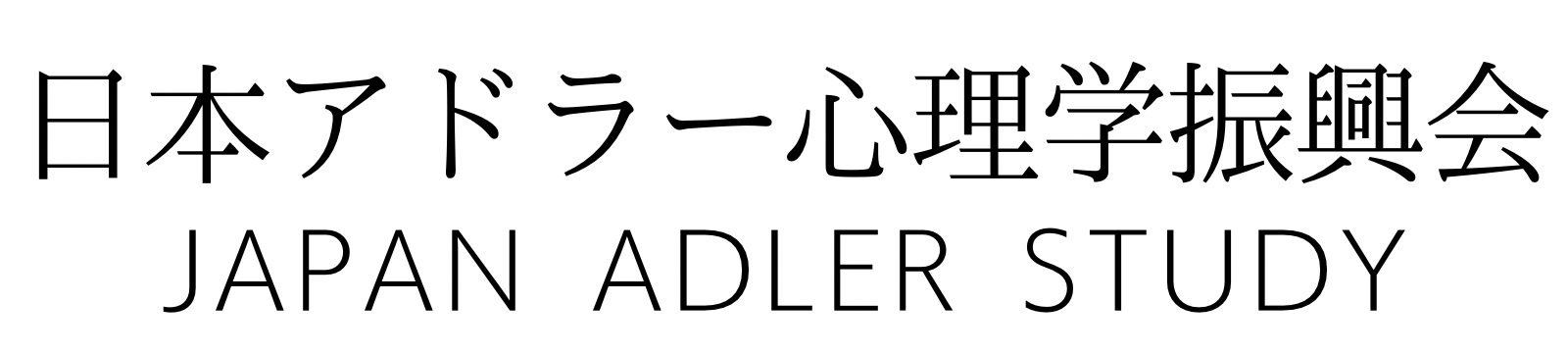


コメント